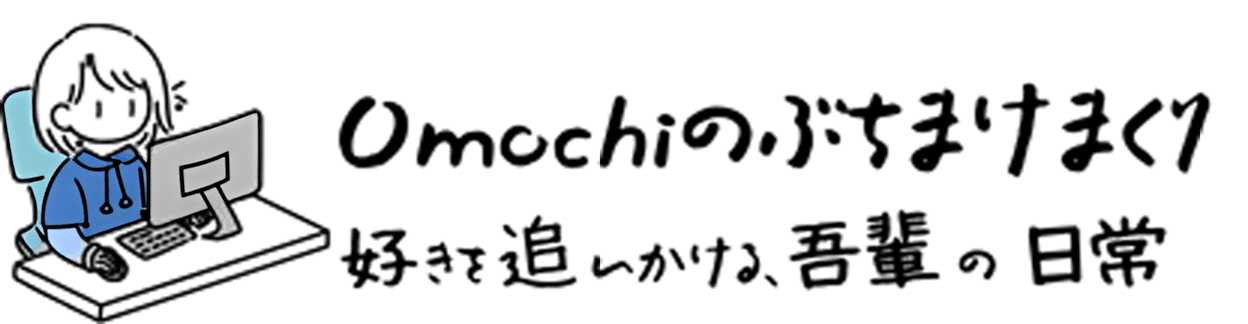記事公開日:2018年3月22日
最終更新日:2025年2月18日
「アメリカのご家庭にピッタリの、ルガーMk-1」。銃国家と名高い欧米でも、みんながみんな扱いに長けるわけじゃない。
誰だって、初心者の期間があった。
今回はスターム・ルガー社が開発したロングセラーモデルを、台湾のエアガンメーカーが製品化したものに迫っていこう。KJ WORKS製のMk‐1をレビューしていくので、色んなところを心ゆくまで観察していくよ。
カスタムの土台に良いモデルかな。
KJワークスのルガーMk-1
このあと出てくるMk-1という銃は、第二次世界大戦終結後の1950年に、アメリカで産声を上げたモデルだ。開発はスターム・ルガー社。ここが初めて作り出した自動拳銃として名を残し、実に長い間ずっと生産されているものなのだ。現在でも造られている。
なぜかと言うと、価格が安い上に性能も中々良い。そして使う弾の火力が弱めという弱点こそあるものの、代わりに扱いやすい。アメリカではまさしく、拳銃を初めて触る初心者向けの入門品として愛されている模様。

そんなルガーMk-1は、エアガンとしてもいくつか製品化されている。国内メーカーならマルシン、海外ならばKJ WORKSが主。吾輩が手に入れたのは後者で、現在所持するハンドガンの中ではただ一つの海外メーカー製。通常であれば、内部洗浄は必須と言われる。
しかし、KJ WORKS製であればそこそこの射撃能力を備えるので洗浄はしてもいいけど必ず、というレベルではないのがありがたい。

KJのルガーMk-1は色々あるけど吾輩のは本体色がブラックのABSで、固定ガスガン。カービン化キットも存在する。今回は単品のみのレビューなので、そこはご了承願うよ。
何かしらいじる前提のモデルかなぁ。
レビュー開始

パッケージは紙製のよくあるものだが、表面は中々凝ってる。革やライター、弾丸と本体など雰囲気を盛り上げるアイテムが写る。

フタを取り外すと、白のごく普通な型抜き発泡スチロールが見える。そこに本体、マガジン、少量のBB弾や取説など。本体はビニールで保護されてるが、吾輩の個体は表面が少し油っぽかったのでティッシュで拭いた。


取り出して本体の外観。ルガーMk-1の特徴といえば、グリップ上部から伸びたアウターバレルのみの見た目。まさに古き時代に生まれたのがよく分かる、現代基準で考えると古風な感じがかっこいい。
この銃を見るとメタルギアソリッド4で麻酔担当として登場した、マイナーチェンジ版のMk-2を思い出す。ムービー長すぎ。

本体には一切刻印が彫られておらず、完全に無地。一応写真のように台湾製のシールだけ、申し訳程度に貼ってある。ダサいので、慎重に剥がしてさっさと捨てちまおう。


銃後方のハンマー部分は、完全に内部へ隠された仕様。そのため、服は引っ掛けないけど発射可能かどうかが少々わかりにくい。別でレビューしたワルサーP99のように、インジケーターが見えるわけでもないので。
記事公開日:2018年2月6日最終更新日:2025年2月12日 「射撃しやすい固定ガスガンの、決定版モデルといえば?」。そこにはトリガーの引き心地が最も大きく関わる、決して無視できない要素。スライドが固定されて[…]
セーフティは2枚を見比べよう。黒丸が上にあれば解除、下にすればロックが掛かる。赤色とかあればもうちょい良かったのに。


リアサイトから覗くと、こんな感じ。リア・フロント共に固定のサイトで、本体と同じく完全に真っ黒。まぁ普通かな。


トリガーはよくある三日月型のツメタイプ。可動範囲はそこそこ。固定ガスガンなので、引き金は少々重ためで力が必要。まぁマルイのSOCOMよりはマシだけど、マルゼンのワルサーP99ほどスムーズには引けないね。
またそれとは別に厄介な問題があり、トリガーガードの隙間がめちゃくちゃ狭い。特にグローブを嵌めた状態だと、指を入れにくいのが困りもの。もうちょっとゆとりをくれ…。




グリップはツルツルの樹脂だが、細かいダイヤ状のチェッカリング入り。指の窪みである、フィンガーチャネルもない、非常にシンプルなもの。ただ、比較的薄いので手が小さめな日本人でも、きちんと握り込めるのはありがたいところだな。


この中の珍しい特徴がここにもあって、グリップの後面にパーツが仕込まれてるのがわかるかな。これ、通常分解のための部分。




一枚目の写真にあるツメの下を押すと、上側が浮き出てくる。そのままゆっくり引っ張ると、接続されたパーツが付いてくるのよね。さらにパーツ全体を下にずらすと、見事に引っこ抜けるのだ。ここまで来たら、スライドを動かして通常分解ができるようになるよ。
戻すときは逆の手順をすればおk。ただし注意点があって、最初にツメを元に戻さないとダメ。これをしないと戻らない。当初戻せなくなって焦った吾輩は、5分ほど苦戦して戻せた。ただ途中で手を挟み、内出血を起こしてすげえ痛かった…。マジで慎重にやろうね。






マガジンの外し方が、いわゆる旧式の銃によくあるタイプ。ロックをかけるツメが底にあるので、ずらしてから外せるようになるよ。現代のモデルで標準な、マグキャッチボタンではないので注意。ボタンポじゃないので、慣れないと素早い操作が難しい。




最後はマガジン。あ、ちょっと写真がボケちゃった。刻印は本体と同じく全く彫られていない、飾り気のないもの。薄めの作りだが、固定ガスガンなのである程度冷えに強い。
総評はそのままでは輝かない
それじゃあ最後のまとめに入るね。まず、良いところと悪いところを列挙しておく。
・トリガー周りの配慮がイマイチ
・マガジンの固定方法が旧式
・手に入れづらい
・グリップが薄いので小さな手でも問題なし
・値段自体は比較的リーズナブル
表面の質感においては、ぶっちゃけ価格相応。チープ感が強いかなぁ。同じ黒でも、国内メーカー製のほうが重厚感はあるよね。
他の部分は、まぁ実銃譲りの利点と欠点なので、メーカーがどうのこうのじゃない。値段については、確か実売価格が約8,000円とお求めやすい価格。ただし海外製ゆえ、潤沢な流通量とは言えないのも難しい。


残念ながらそのままであれば、決して高い満足感を得られるモデルではない。ただし、逆に言えば磨いて光る可能性は十分にある。つまり我輩的には、ペイントカスタムの土台として、自分好みの色に染め上げていくのが良いベース品っていう印象だと思ったよ。
特に初めてエアガンの塗装に挑戦するって人なら、このMk-1は割とアリなんじゃないかと。入手できればの話だけどね。
改造の練習台には良さげ。


今回はここまで。Mk-1のエアガンは、マルシンかKJ WORKSしかないので、どちらにせよ入手性が良くない、貴重なモデル。