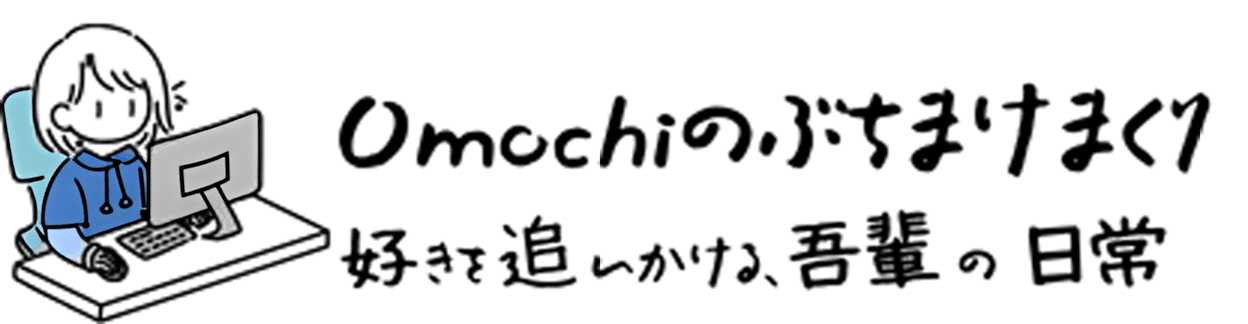記事公開日:2025年7月25日
全部CUDAが原因だった。吾輩、今年に入ってからStable Diffusionに興味を持ち、色々イラストをAI生成して使えるかどうか試してた。
使い始めてから3ヶ月くらいは、特段大きな問題も無くちゃんと生成できてたんだよ。グラボが古いので、高解像度は無理だったが。
そこで数年ぶりにグラボを新しいのに変えて、RTX2070Super→RTX5060Tiにパワーアップしたのだが、そのあとからしばらくいばらの道が続いてしまった。
今回は、現時点でRTX5000番台でStable Diffusionを使いたい人向けに、エラーを回避する方法を教えるよ。フタを開けて見れば凄い簡単なことだった。
reForgeに変更してくれ。
Stable Diffusionのエラー
このソフト、プログラミングの知識が無いと導入するハードルがちょっと高い。が、幸い一括インストールできるソフトが今はあるのでそれ使えば大丈夫。
Stability Matrixというやつで、我輩も最初からこれに頼っていた。というか後述のエラーを解決した後も、結局コイツのお世話になりっぱなし。導入に関しては↓。
当ソフトは今、NVIDIAのGPUとの相性が良いのでこれをPCに組み込むのが半ば前提。本記事執筆時点で、最新世代と言えばGeforce RTX5000番台の子たち。
なんだけど、Stable Diffusionの中にあるプログラムと、RTX5000番台のグラボは色々あって最適化が進んでおらず各所でエラー報告が相次いでいるのが現状。吾輩のPCでも同じ。

数日間、ChatGPTを頼りにしながらトラブルシューティングをして、何とか解決できたのでその方法を共有しておく。ぜひ参考に。遠回りした結果、めっちゃ簡単な方法で回避できた。それはStable Diffusion WebUI reForgeを使うことで、エラーは避けられたよ。
こだわりなければこれでOK。
CUDAのバージョンが合わない
本ソフトでエラーが起きる原因は色々あるけど、この5000番台で頻発するのはCUDAエラーというもの。英文は別に読まなくていいけどこんなメッセージが出た。
TORCH_USE_CUDA_DSA to enable device-side assertions.
要はGPUに含まれたCUDAというプログラムが、Stable Diffusion上だと最新に最適化されておらずエラーだよってこと。つまり、CUDAのバージョンが上がればOK。
ついでにPytorchというものも、バージョンを上げないとうまく適合しないんだけど、その辺は吾輩も正直良く分かってないのでそうなんだーくらいで捉えてもらえば大丈夫。

で、じゃあどうやってバージョンを上げるかと言うと、プログラミング知識がない人間にとってはわかりづらい上に大変極まりない。
コマンドプロンプト、WindowsPowershell等に専用のコマンドを打ち込むしかないのだ。コード自体はChat GPTに聞けば教えてくれるから、ノーヒントではないが。
そもそも吾輩は、この辺のアプリを使うほど知識が無いので画面を見ただけで?マークしか浮かばないレベル。意味不明すぎて本当に困った。どうやれとって感じ。
バージョン上げ失敗の連続
Stable Diffusionはプログラミング言語を動かすと、ブラウザが自動で立ち上がって使えるようになるもの。これ、複数のGUIと呼ばれるものが提供されてるのね。GUIというのは、いわゆるユーザーインターフェースで画面の見栄えやデザインのことを指す。
Stable Diffusionでは、いくつかメジャーなGUIがあり元祖のAutomatic1111、派生のForge、そのまた更に派生のreForge、他にもComfyUIなどあるから好みで選べる。

吾輩の場合、元々グラボ交換前は一番利用者が多いAutomatic1111を使っていたんだが、交換後にこれを使おうとするとさっきのCUDAエラーが出ていたんだ。
で、CUDAバージョンを更新しようとして、慣れないコマンドプロンプトをいじりまくったのだが、何をやっても更新できない。多分7通りくらいやったかも。目的はブラウザの下部にある、Pytorch+cuとある部分で、このcuが122以上になればOKなのだが、どうあがいてもバージョンが上がらない。弾かれまくり。
Automatic1111、実は2024年に開発が終了をしていて開発側で更新がそもそもされていないのだ。だからユーザーが自力で更新するしかない現状にある。しかしそれをやろうにも、適切なバージョンがネットで見つからないなどの弊害で手も足も出なかったのが、本当に困ってたんだよね。

当初はStability Matrixのアプリ経由で何とかできないか粘ったんだけど、うまく行かなかったから従来の方法でStable Diffusionを再インストールしたり…。そのうえでバージョンをどうこういじったんだが、何度プログラムを動かしてもCUDAバージョンが121で止まってしまう。もうこれは詰んだか…。
reForgeの存在を思い出した
このStable Diffusion reForgeという別のGUIがあったことを思い出し、ダメ元でStability Matrixからのインストールを試したの。
元祖のAutomatic1111に比べ、最初からある程度の拡張機能が入ってたりグラボの使用効率が上昇した別種の改良版的なもの。
諦めつつもインストールを進めると、途中のコードでよく記述されていたRuntimeERRORが出てきてないような様子が見て取れた…。

ブラウザが立ち上がるまでは今まで通りだが、ブラウザ下部をよく見るとtorch2.7.1+cu128と表記されていたよ。あれ?、さっきとメッセージがなんか違うぞこれ?

そこでプリインストールされたモデルを選択し、従来通りに生成ボタンを押してみたら、普通に画像が作れた。マジかよイケんのか!

どうやらこのreForgeは開発歴史をひも解くと、2025年の春に開発終了が宣言されたのだが同年夏ごろに細々と開発は続行するよという声明があってね。
RTX5000番台にもちゃんと適合するよう、PytorchとCUDAバージョンが合わせられるように自動で作り直されていたみたいだ。
本当に助かった…。

まぁAutomatic1111が使えない現状自体は変わっていないんだけど、reForgeも見た目がほとんど変わらないからこっちでも問題なし。
当面はこちらを使う予定だ。
reForgeに変えてみよう
というわけで、Stable DiffusionとグラボRTX5000番台のソフトウェア的相性が悪いため、起こった超めんどくさいトラブルだったよ。二度と原因を探りたくない…。
吾輩と同じ現象になっている人は、GUIそのものを全然別物に変えるという選択肢があることを知っておいてほしい。それで解決するかもしれないという希望を持って。
reForgeでもいいし、それ以外のものでもCUDAバージョンとグラボが最適かされていれば問題なく動くはずなので。困ったら試してみてほしい。イケるかもしれん。
元の環境は一旦捨てろ。

余談:最新世代は不安定
今回の件で良く分かったことは、グラボというのは最新世代が常に正義であるわけじゃないということ。今までは値段という観点でしか考えてなかった。
しかしグラボ(ハードウェア)が新しくとも、各種プログラム(ソフトウェア)の対応が追い付かないという、単純なことを完全に忘れてたよ。だから全部新しければ良い、というのはケースバイケースなんだね。
ちなみにChat GPTにも、過去Stable Diffusionで似たような問題が起きていたかどうか聞いたところ、どのグラボの世代でも発売したてのころはあった模様。
つまり毎回のように起こっていることであり、今回に関係ないどのアプリケーションでもあるあるなことだって話かな。まぁそれはしょうがないだろう。

今回はここまで。ひとまずreForge環境ではあるものの、画像生成が出来るようになったことには変わらない。こんなに苦労するとは思わなかったが、無事に何とかなった。