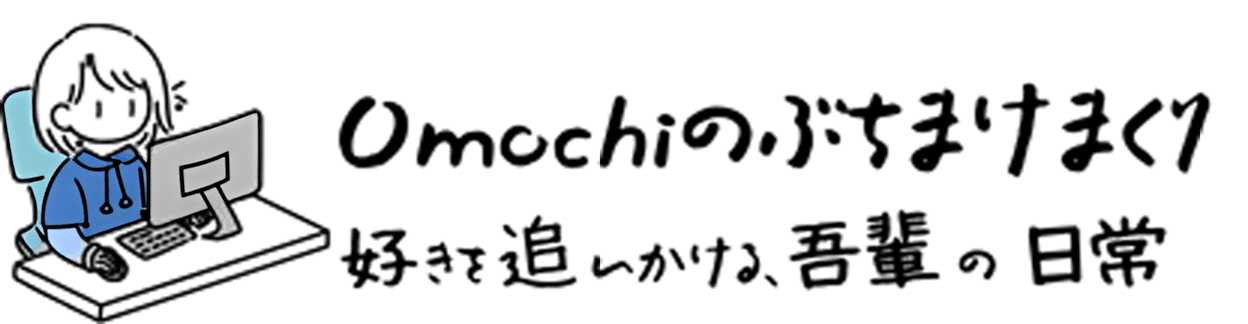記事公開日:2021年1月9日
最終更新日:2024年12月20日
「少しずつ、完成形のイメージが見えてくる…」。マザーボードの作業が終わったら、見た目の印象を決めるPCケースの出番。
実際に各パーツを組み込もう。
今回はマザボ、電源ユニット、ケースファン、PCケースの出番だ。加えてドライバーでのネジ締めが増えてくる。準備はできた?
自作PC組み立てのおさらい
まずは軽く、前回の復習をしよう。マザーボードへ、以下のパーツを取り付けたよね。
・CPUクーラー
・メモリ
・M.2SSD(使うのであれば)
記事公開日:2021年1月3日最終更新日:2024年12月19日 「パーツが揃ったら、初めての人でも完成にこぎつけられる」と思いたったところ、気づけば自作PCの道を歩み始めていた。今回から5回分に渡り、自作PC[…]
特に、CPUクーラーの取り付けが手間取ったな。単純にネジが全然入らなくて、かなり焦った記憶が…。あと、CPUを壊さないように慎重な作業が多かった。この辺りが、一番神経をすり減らしたかも。今回は多分、あまりそうはならなそうな感じ。


まぁ気を取り直して、パソコンの顔とも言えるケース。これで、パッと見の形が見えてくるね。好きな外見にできるから、自作は自由度が本当に高いのよ!
使うケースの仕様はしっかり把握


パソコンの中でも最大サイズを誇る、ケース本体とパッケージ。とにかくデカく、作業場所は広く確保すべし。ケースごとにやり方が変わるので、付属の取説はよく読む。
今回使うのは、Themaltake製のVersa H26というやつ。ベースモデルじゃなく、初音ミクさんのコラボモデル。ちなみにH26自体は廉価帯のケースで、ネットでの使用者も多いみたい。大きさは、ミドルタワーに分類される。


まずフロント側から。上段は5インチベイで、DVDプレーヤー等が入れられる。中段と下段はメッシュの隙間がある。この裏側にケースファンを設置して、空気の吸引を行う。


ケースのバックパネルは、写真左側の部分。上段には、付属のファンが最初から一つ付いてる。もちろんそのまま使ってもいいし、不要なら取り外しちゃっても大丈夫。
中段の水色部分は、グラボなどを取り付けるプレート部。ここに、HDMIやらDPの映像用ケーブルを接続する予定。下段は、電源ユニットの格納場所にあたる。
右上にあるのが、光学ドライブの収納スペース。イマドキは使わないことが多いので、吾輩は外して場所を空けたよ。
記事公開日:2021年2月23日最終更新日:2025年11月13日 自分好みの満足なスペックで自作PC(あるいはBTOの注文)を組んでるとき、ケースのベイにぽつんと空いた穴を見て「光学ドライブあったほうがいいか[…]
更に写真では外した後なんだけど、手前にアクリルパネルが付く。側面からPC内部が透けて見えるので、光らせたいなら必須やな。




反対サイドは、真っ黒の板のみ。四か所がねじ止めされており、外すと板も取れる。その板を取った後が、この2枚目の写真。
右上は、配線整理用のゴム穴が6つ。その下はシャドウベイで、SSDやHDDを入れていく。左上の大きな穴は、マザボを取り付ける場所。左下は、電源ユニットを入れる場所。
フロントパネルを引き剥がす
さっそくマザボをと言いたいけど、その前にフロントパネルを先に剥がして、この後の作業を楽にしておこう。


パネルの裏側。写真だとわからないけど、樹脂の爪で引っかけて固定されてるのね。ここが一つ目の難所だった。取説を見ると、力任せに前から剥がせばいいとのことだったんだけど…。全然剥がせる気がせず、裏から爪を外せないか悪戦苦闘したのよ。
数十分格闘したけどやっぱりダメ。諦めかけたがダメ元でもう一度パネルの前に立ち、更に力を込めて引っ張ってみると…。
急にバコン!と音がしてようやく外れたよ。ケースを壊すかと思う勢いじゃないとダメ。女性だと開けるのはかなり厳しいかも。


上から、何本ものケーブルが伸びてる。これをマザボに接続すると、外についてるUSB端子やら電源ボタンが機能するようになるよ。とりあえずケーブルも含めて、一旦ケースから完全に分離させよう。
マザボをケース内に収める
前回完成させた、マザボ一式をケースに入れていこう。ただしその前に、I/Oパネルがマザボに付いてるか確認してね。もし付いてない状態でケースに入れると、後で面倒なことになる。吾輩のやつは元から付いてたけど、自分でつけなきゃいけない場合もアリ。


まずケースを横に倒して、サイドパネル表側を上にしよう。更に内部に黒くて丸い、スペーサーがあるので全部外す。全部で9か所あった。加えてマザボをねじ止めする用のネジがあるので、それを用意する。










そしたらスペーサーの位置に合わせ、マザボを上から被せるように。お互いのネジ位置と必ず合うので、それを目安にしてみてね。あとは9か所を全てねじ止め。スタート地点から対角線上に、ネジを半分程度回す。半固定が完了したら、増し締めを行うよ。
なぜか中央だけネジが回らず、8か所しかできなかったんだけど…。まぁ固定できたし大丈夫やろ。これでマザボはOK。


5インチベイを外す
この部分を残したい人は、やる必要が無い作業。吾輩はベイがある部分にケースファンを付けたいため、ここを取っ払う。


これは外すのが簡単で、数本ねじ止めされてるだけだった。手でベイを支えつつ、ネジをどんどん外そう。
フロントにケースファンを付ける
次はケースのフロント部に、ファンを取り付ける。ミクさんコラボのRGBファンを2つ。元々付属してたファン1つで、合計3基に。


縦に3つを並べて、一番上だけ付属の光らないファンを設置。フロントパネルを戻すと、実際見えるのは中段と下段だけなので。
そこが光るファンであればOK。


正面からそれぞれ四隅をねじ止め。空気の吸引をするので、ファンの向きには気を付けよう。フレームに風が流れる向きがある。
電源ユニットをケースに収める
次は電源ユニットの取り付け。まず本体に、各種ケーブルを取り付けるぞ。今回使うのは、プラグイン形式と呼ばれるタイプのモノ。必要なケーブルだけでよく、本数を少なく管理しやすいぞ。


M/Bと書かれた端子に接続するケーブル。もちろん、マザーボードとつなぐやつだ。




上がCPUへの電力供給、下がGPUへの電力供給を担うケーブル。似てるので少々紛らわしいが、端子の数がちょっと違う。


シャドウベイに格納した、HDD&SSDに電力を送るSATAケーブル。ケーブルの途中で、SATAの端子がいくつもくっついてる。


ファンコントローラーにつなぐ、MOLEX端子のケーブル。RGB発光するファンには、大体コントローラーがあるのでそれの電力供給用。場合によっては、不要なケーブルの一つ。


電源ユニットのRGB発光制御用ケーブル。光らないタイプのユニットにはおそらく無い。


コンセントと電源ユニットをつなぐケーブル。ある意味一番大事で、これだけビニールの被膜。ケーブルにはどれ用のモノなのか、パーツ名が書いてある。あるいはピンの数や端子の形で、どこに使うか判別できるよ。


必要な分を取り付けた。うーん、やっぱりそこそこの本数を使うな…。


あとはそのまま、PCケースに格納していく。ゴリゴリと押し込んでいこう。厄介なことに、そのままユニットを入れると問題が。
すぐ隣にある、シャドウベイとケーブルが干渉して入りきらない。ケーブルが硬くて、全然押し込めん。しょうがないので、一旦シャドウベイも全て取っ払うことに。


無事に?電源ユニットが入った。細かいケーブルの配線は、とりあえず後回し。




あとは、電源ユニットをねじ止めしてあげる。これも四隅をロックすることで、しっかり固定されるので忘れずに。
付けて外してを繰り返す
とりあえず作業はいったんここで区切ろう。精密な作業というより、力押しの作業が増えてきた。あとネジとの闘い。とはいえ、ちょっとずつデスクトップの片鱗が見え始める頃合い。完成が楽しみになってきた~!


今回はここまで。次は残りのパーツ組付けと、ケーブルの配線をどんどん進めていこう。全体の半分は過ぎてきたかな!
記事公開日:2021年1月12日最終更新日:2024年12月20日 「作業が全て終わると、そこには理想のデスクトップが...。」完成の暁には、念願の自分だけのパソコンが出来上がる。地道に進めれば、必ずできる[…]