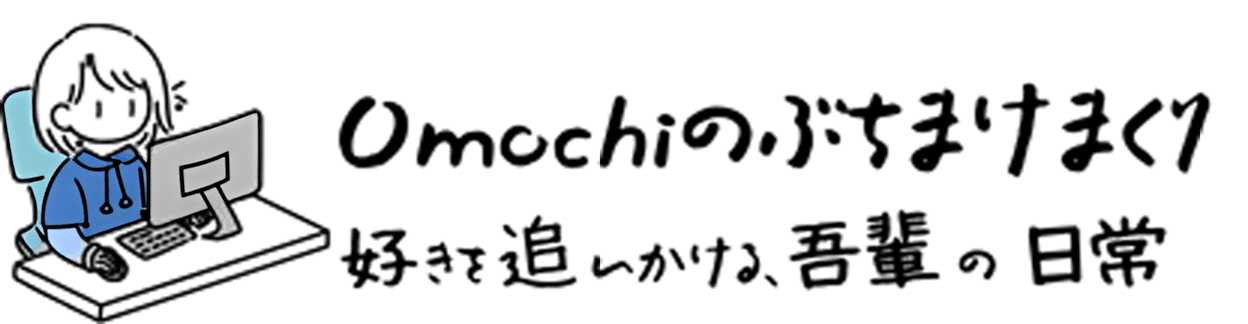記事公開日:2021年1月12日
最終更新日:2024年12月20日
「作業が全て終わると、そこには理想のデスクトップが…。」完成の暁には、念願の自分だけのパソコンが出来上がる。地道に進めれば、必ずできるから頑張ろう。
今回は残りパーツの組み込み。
ここでようやく、外装の完成までたどり着ける。さぁ行ってみるか!
前回はパーツを組み込み始めた
あらためて、前回のおさらいをしよう。PCケースに、マザボやら電源やらを組み込んできた。半分くらいは、形になってきたと思う。

記事公開日:2021年1月9日最終更新日:2024年12月20日 「少しずつ、完成形のイメージが見えてくる...」。マザーボードの作業が終わったら、見た目の印象を決めるPCケースの出番。 […]
ケーブルの配線は、最後にすべて整理していくよ。それまでは残りのパーツをどんどん付け足そう。またまたネジが大量に来るので、気合を入れて締めていくぞ。
順番待ちのパーツをどんどん設置
今回の作業の流れはこの通り。
↓
シャドウベイに内臓ストレージをセット
↓
残りのケースファンを全て装着
↓
全てのケーブルを正しく繋いで配線整理
↓
完成
まだ使ってなかったGPUなどが、ここでようやく登場してくる。あせらず確実に、作業を進めていこう。時間がかかっても、慎重に進めていけば絶対に大丈夫なんだから。


マザボへGPUを接続


CPUと双璧を成す相方であるGPU。これをマザボにくっつけ、ケース内に固定させよう。




まずバックパネル中段にある、細いプレートを取る。ねじ止めされているので、両端をドライバーで外す。ちなみにケースによっては、直接折り取るパターンもあるよ。
上から2段目より、プレートをケースから分離させる。一番上は、つけっぱなしで大丈夫だった。また何枚外すかは、GPUの厚みによる。必要スロット数を調べておき、小数点以下切り上げの枚数を外そう。




プレートが外せたら、マザボの表面を。横に長い端子が見つかると思う。PCIEスロットと呼ばれるもので、ここにグラボの薄くて細長い端子を繋げるのだ。
ファンを下に向けた状態で、そっと差し込む。カチッと音がしたらOK。そのあと、さっき外したプレート部分とグラボをねじ止め。これでGPUがケース内に固定。
内蔵ストレージをケース内へ


次はシャドウベイに、各種ストレージを内蔵していくよ。今回使うのは、右が3.5インチのHDD。左が2.5インチのSSD。サイズが違うけど、大概のベイ自体は両方の大きさに対応する。なので、安心して使おう。
前回は電源ユニットをケースに入れたとき、シャドウベイが邪魔過ぎた。なので、先に一度取り払った。無事にユニットを入れた後に、もう一度ベイを取り付けなおす。


このPCケースは、樹脂製のトレイがいくつかある。今回のは3段分あったかな。引き出しのように引っ張ってね。そしたらトレイの溝に、ストレージ側のネジ穴を合わせる。後は、四隅をまたねじ止めするだけ。
向きに注意。写真のように、SATA端子が手前に来るようにしてね。後で電源供給用ケーブルをつなげるので。
残りのケースファンを装着




前回もやった、ケースファンのセットだ。あと残っているのは、ケースの天井3つ分とバックパネルの1つで合わせて4つ分。こっちは空気の排気を行うので、向きを注意しよう。ねじ止めのやり方は前と変わらず。




やっぱり同じ種類のファンが3つ並ぶと、整然としてるね。いやあ、これが良いんだよ…。
ケーブル接続&配線整理作業
ここまでくれば、必要なパーツは全てケース内に収まったが、まだ接続しなきゃいけないものがある。先にPCケースとマザボに繋ぐやつから行こうか。


めっちゃ硬いフロントパネルについてた、複数のケーブル。こいつを、マザボの隅っこそれぞれに繋ぎ合わせる。これで、PCケースのUSBや電源ボタンが使えるようになる。


USB3.0を使用可能にするケーブル。青くピン数が多くてわかりやすい。


こっちは、USB2.0を機能させるケーブル。


HD AUDIOは、ピープ音を出すためのケーブル。これはPCに何らかのエラーが起きたとき、音で問題を知らせてくれるためのもの。


先端が複数に分かれるケーブル。ケースの電源ボタンを機能させるやつで、今回の難所ポイント。正しく接続しないとダメなうえに、場所がかなり厄介。マザボの右下に繋ぐのだが、狭くてかなり繋ぎづらい。
専用の補助アイテムがあったので、それに助けられたなぁ…。そのまま挿せって言われたら、多分心折れてたと思う。よくマザボの取説をチェックしながら、力任せにならないように指してくれ。


次は、電源ユニットから伸びるケーブルの処理だ。最初はGPUの端子を繋ごう。


こっちは、内臓ストレージに電力を供給するケーブル。一本で、複数のストレージをつないでいこう。あ、CPUへの電源供給ケーブルの写真を撮り忘れてた。これもマザボの端子と、電源ユニットをつないでおいてね。
最後はケースファンのケーブル。ファンの仕様ごとに、接続場所が変わってくるので注意。PCケース付属のファンは、マザボに直接つなげる。どこかにCHA~FANと、書かれた端子があるはず。そこにぶっさせば大丈夫。
3ピンと4ピンがあるけど、付属のやつは3ピンのコネクタ。ピン数が違うけど、そのまま挿しちゃって問題なし。ちなみに3ピンはただファンを回すだけ。4ピンはそれに加え、回転数をマザボで制御できるようになるもよう。


厄介なのが、いっぱい設置したミクさんファンのほう。これはUSB2.0端子でつなぐのだが、6基分あるので…。マザボに接続するには、明らかに端子数が足りない。だから、ファン専用のコントローラーを使う。


ケースファンの取説を読みながら、つなぎ方を確認しよう。まずファンコンに、各ファンにあるケーブルを全部繋ぐ。1台につき5基繋げられるが、2個のファンコン×3基ずつにしたよ。ちなみにこれ、最大でファンコン5台×16基=80のファンが同時制御可能。
果たして、最大数使うアホみたいなパソコンは存在するのか。


コントローラー同士をつなぐケーブル。加えて、マザボのUSB2.0ピンに使うケーブル。


こっちはファンコントローラーと、電源ユニットをつなぐケーブル。今はあまり見ない規格のMOLEX端子。すげえ硬かった。
ケーブル数がすごく多いので、初見だとかなり迷う。端子の穴と、ピンの形が適切かよく見よう。ピンを曲げないよう、無理に力押しで差し込んじゃダメだよ。
最後の最後で面倒な配線作業


残りは配線作業のみで、結束バンドがかなり役立つ。あと、ファンにケーブルが巻き込まれないようにしてね。非常に危ないので。
全て完了したら、裏側のサイドパネルを閉める。かなりぎちぎちなので、結局力押しで入れるしかなかった…。もうちょい裏配線スペースに、空間の余裕が欲しかったところ。


これで組み立ては完成!。最後に、表のサイドパネルでふたをしよう。
自分で組んだパソコンは神々しい
長い旅路を経て、なんとか完成まで仕上がった。途中苦労するポイントはあったけど、ひとまず見た目上は問題無さそう。やることは単純なので、順を追えばそう難しくはない。2日間かかったけど、すげえホッとした…。


後は無事に電源が入れば、95%の作業終了だ。しかしこの後、案の定というかトラブルが発生してしまうのだった…。
今回はここまで。実はまだもう一回あって、トラブルシューティング回になる。加えてOSインストールもやるので、ぜひご覧あれ。
記事公開日:2021年1月15日最終更新日:2024年12月21日 「組んだPCを無事に起動できれば完全に終了!」そう、形が組みあがってもまだこれが残っている。起動とOSのインストールだ。今回で、自作PCの[…]